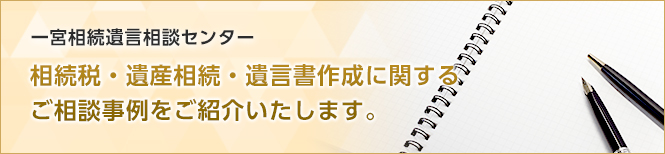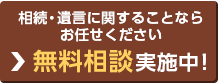2019年11月16日
Q:相続税の申告手続きは自分1人でできますか?(一宮)
私は現在、一宮に社会人の息子と住んでいます。先月夫が亡くなり、その相続の手続きをしなければなりません。相続人は妻である私と息子になると思い、二人で話し合いをしました。相続税の控除なども息子がいろいろ調べてくれたのですが、亡くなった主人が所有していた家や土地や預金なども合わせおおよその相続財産の価格を計算してみたところ、やはり相続税がかかりそうです。私は、相続税の申告手続きの他にもやらなければいけないことがたくさんありますし、知識や経験がないので専門の方にお願いしようかと思っていたのですが、息子は自分自身で計算して相続税を申告するので大丈夫だと言います。私は万が一でも計算間違いがあってはいけないですし、息子には仕事もあり忙しいと思い、私と息子の2人の分を最初から専門家へ依頼した方がよいのではないかという不安があります。知識や経験のない息子が1人で申告手続きをしても大丈夫でしょうか?(一宮)
A:ご自身だけでも相続税の申告は可能ですが、税理士に依頼すると安心です。
税理士は、相続税申告の専門家ですので、税理士へ依頼する方が安心です。と言いますのも、相続税申告は内容が複雑であり、十分な理解をせず申告すると不明瞭な点や間違いが出てきます。こういった場合には、本来の税金の他に過少申告加算税や延滞税が課されることが考えられます。
また、相続税には申告の期限が設けられていることにも注意が必要です。申告するには遺産分割が済んでいる事が前提ですが、この遺産分割の協議にも様々な手間や時間がかかる事が多いです。そして、やはり遺産分割が終わったらすぐに相続税申告にとりかかることをお勧めします。申告期限を超えてしまうと延滞税などのペナルティが発生してしまうからです。一宮のご相談者様の場合、遺産の中に家と土地が含まれますので、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に煩雑になると思われます。
一般の方だけで手続きをすることも可能ですが、膨大な手間が掛かるうえスピードも求められますので、多くの方が税理士へ相談したり申告業務の代行を依頼したりしています。税理士に依頼するということは、上記のような問題を未然に防ぐために大きな力となります。
相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。無料相談実施中なので、相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、わからないことやご不安に感じていることがあればお気軽にお電話ください。
2019年10月11日
Q死亡保険金は相続税申告の際、どのような扱いでしょうか?(一宮)
生まれてからずっと一宮に住んでいます。私は結婚をして実家を離れましたが、両親と私の兄は一宮の実家に一緒に住んでおります。長期にわたって闘病生活をしていた父が先日他界しました。覚悟ができていたとはいえ、悲しんでいる余裕もないまま相続税のことを考えなければならず、焦り始めています。とりあえず葬儀については私たち親族の慣れ親しんだ一宮で滞りなく執り行うことが出来ました。相続税の申告については期限があると聞いていたので、葬式の際に兄と、父の遺産とそれにかかる相続税の話をしました。父の遺産総額をざっと調べてみたところ基礎控除額を超えますので、やはり相続税の申告をしなければならないようです。相続人は母、私、iti実家で同居する兄の3人です。また、相続税の申告手続きの話し合いの中でわかったのですが、父が亡くなった際、母が父の死亡保険金を受け取っていたそうです。契約内容を確認すると、金額は2000万円で、父が契約者と被保険者、母が受取人です。死亡保険金の扱いについて、受取人の財産になり相続税はかからないと聞いたとこがあるのですが、相続税申告はどうなるのか教えてください。(一宮)
A 生命保険金や死亡退職金は非課税限度額以下の時は相続税の課税対象とはなりません。
生命保険金や死亡退職金は、基本的に相続税の課税対象となるのですが、法定相続人一人当たりにつき500万円の非課税限度額があり、それを超える部分に関しては課税対象になるのでご注意ください。
死亡保険金の非課税限度額の計算方法(適用できるのは相続人が受け取ったもののみです)
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数(今回のケースではお母様とお兄様、ご相談者様の3人)
2000万円-1500万円=500万円
つまり2000万円の死亡保険金のうち500万円は相続税の課税対象になるということです。
この法定相続人というのはご相談者様の場合、ご相談者様とお母様、お兄様の3人になりますので、500万円×3人=1500万円が非課税限度額になります。
死亡保険金は、ご相談者様のご指摘のように、民法上受取人固有の財産として扱われますので相続財産には含まれないとされ、遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象として扱われるのです。
気を付けていただきたいのが、契約者(保険金の支払者)=被相続人において相続税が発生します。今回のケースでは契約者はお父様ですので問題ありませんが、かならず保険契約を確認してください。
相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。一宮近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
2019年09月17日
Q 孫に生命保険金を渡すと相続税対策になるのでしょうか?(一宮)
一宮で長年会社経営を行っている70歳の男性です。事業に関しては既に引退し、息子に引き継いで余生を楽しんでいます。そろそろ終活を始めなければと思っているのですが、一番の心配は相続税の問題です。私の資産を考えると将来息子たちが相続税を支払うことは確実です。同じく一宮に住む経営者仲間に生命保険金で対策ができると聞いていたので、2人の息子を受取人に契約をしておりますが、この度長男の息子を受取人とした生命保険も行うか考えています。孫が生命保険金の受取人になる場合、相続税はどのような扱いになるのでしょうか?(一宮)
A お孫様の受取る生命保険金も相続税の課税対象です。
今回のご相談の場合、生命保険の契約内容は契約者(支払者)=被保険者=ご相談者様、受取人=お孫様とし、お伝えさせていただきます。またご相談者様の相続開始時点での相続人は2人のご子息のみとし、お孫様は代襲相続人となっていないことを前提とします。
生命保険金は受取人固有の財産のため遺産分割協議の対象とはなりませんが、みなし相続財産として、相続税の課税対象とはなります。ただし相続税対策として生命保険金が活用されるは非課税限度額が定められているからです。これにより【500万円×法定相続人の人数】以下の金額の生命保険金に関しては相続税がかかりません。しかしながらこの非課税限度額が適用されるのは生命保険金の受取人が相続人の場合のみなので、残念ながらご相談者様の相続では相続人でないお孫様は対象外となります。また、相続人でない人が遺贈等により財産を取得すると相続税が2割加算されるというルールがあります。それに加えお孫様が生命保険金以外にご相談者様からの贈与を生前に受けていた場合、相続開始から遡り3年以内の贈与も相続税の課税対象となります。お孫様の場合には生命保険金を受け取ったり、遺贈により引き継いだりしない限りこのルールは適用されないので、日ごろから贈与を行っている場合には余計に相続税を支払うことになってしまいます。
お孫様にお金を残してあげたいというお気持ちであれば、教育資金の一括贈与を利用するなど他の方法もあげられます。どの方法がお客様にとって適切かどうか、一緒に検討いたしますので、まずは専門家である税理士にご相談ください。
一宮相続遺言相談センターでは豊富な相続税申告の実績を持つ税理士、専門家の無料相談を実施しております。相続税申告は税理士の中でも税務の他、民法などの正しい知識がないと非常に難しい手続きです。一宮近辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。
32 / 42«...1020...3031323334...40...»